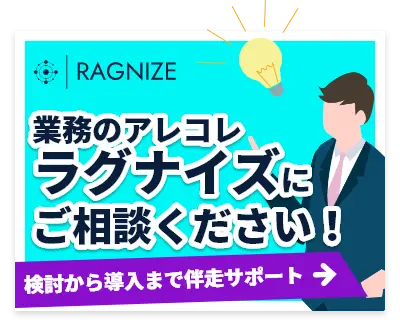自治体業務において住民対応は、自治体職員の皆さんの日常業務の中でも大きな比重を占めているのではないでしょうか。
窓口や電話での問い合わせ対応、各種制度の説明など、丁寧な対応が求められる一方で、本来の政策立案や企画業務に十分な時間を割けないというジレンマを感じている方も多いかもしれません。
本記事では、最近注目されている「RAG型AI」(情報検索と回答生成を組み合わせたAI技術)が、どのように自治体の業務改善に役立つのか、実務に即した形でご紹介します。
こちらも併せてご覧ください:RAG(検索拡張生成)とは?ChatGPTとの違いやビジネス活用法をわかりやすく解説
現場で感じる住民対応の課題

日々の業務の中で、こんな状況に心当たりはありませんか?
- 窓口や電話が鳴り止まず、手元の仕事が進まない
- 担当者が不在の際、他の職員が正確に回答できるか不安
- 制度改正のたびに、対応方法の共有や職員への周知に時間がかかる
- 「〇〇の手続きはどうすればいいですか?」など、同じような質問への対応が何度も発生する
これらの課題は、ベテラン職員の退職や部署異動などで、より深刻になることもあるでしょう。
限られた人員の中で、住民サービスの質を維持しながら業務効率を上げるという難題に、多くの自治体が直面しています。
こんなお悩みありませんか?: 「鳴り止まない電話対応に追われる」「情報引継ぎがスムーズにいかない」という課題をAIで解決する区民相談AIの詳細はこちら
AIで何が変わる?5つの具体的なメリット
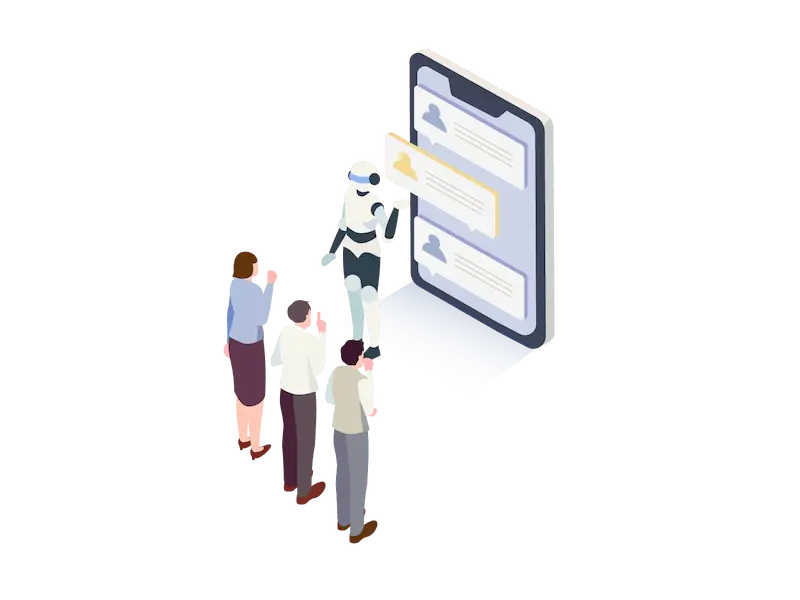
「AI」と聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、実際には現場の皆さんの業務をサポートするための道具です。
RAG型AIの導入によって得られる具体的なメリットを見ていきましょう。
1. 窓口・電話対応の負担軽減
「住民票の取り方を教えてください」「ゴミの出し方が分かりません」といった基本的な問い合わせは、AIが自動で回答できるようになります。
職員の皆さんは、より専門的な判断が必要な業務や、政策立案などの創造的な業務に集中できるようになります。
朝一番の問い合わせ集中時や、昼休み時間の窓口対応など、人手が足りない時間帯でも、AIがサポートすることで業務の平準化が図れます。
2. どの職員でも同じ品質の回答が可能に
自治体では、異動や新人配属など、担当者が変わる機会が少なくありません。
RAG型AIを導入すると、制度やルールに関する情報がシステム内に蓄積されるため、ベテラン職員でも新人職員でも、同じ質問に対して同じ品質の回答ができるようになります。
「○○課に聞いたときと言っていることが違う」という住民からのクレームも減少し、自治体全体としての信頼性向上につながります。
3. 制度改正にもスピーディに対応
年度替わりの制度改正や、急な給付金制度の開始など、情報更新が必要な場面は多々あります。
RAG型AIなら、管理画面で情報を更新するだけで、即座に最新情報での回答が可能になります。
職員全員への周知や、マニュアル改訂などの手間が大幅に削減され、常に最新情報に基づいた住民対応が可能になります。
4.専門性の高い業務に集中できる環境
「いつもの質問への対応」から解放されることで、皆さんの本来の専門性を活かせる業務に集中できます。
例えば、複雑な制度の運用判断、個別ケースへのきめ細かな対応、地域課題の分析と解決策の検討など、「人にしかできない業務」に時間を使えるようになります。
重要なのは、AIはあくまで職員の皆さんの業務を「奪う」ものではなく、「支援する」ツールだということです。
AIが得意とするのは定型的な情報提供や単純作業。一方、住民に寄り添った共感的な対応や、複雑な状況における専門的判断、創造的な政策立案といった業務は、今後も職員の皆さんにしかできない重要な役割です。
AIと人間がそれぞれの強みを活かして協働することで、全体としての行政サービスの質が向上します。
職員の皆さんの専門性が発揮されることで、住民サービスの質も向上します。AIの導入は「人員削減」ではなく「人材活用」のためのものなのです。
5. 24時間365日の住民サービス提供
役所の開庁時間内に来庁や電話ができない住民も少なくありません。
RAG型AIを導入すれば、夜間や休日でも基本的な問い合わせに対応できるため、共働き世帯や子育て世代など、時間的制約のある住民へのサービス向上につながります。
災害時など緊急時にも、避難情報や支援制度の案内を24時間体制で提供できるため、住民の安全・安心を支えるインフラとしても機能します。
業界トレンド: 自治体の職員負担を軽減しながら住民サービスを向上させる最新AI技術についてもっと知りたい方はこちら
導入のポイントと現実的なステップ
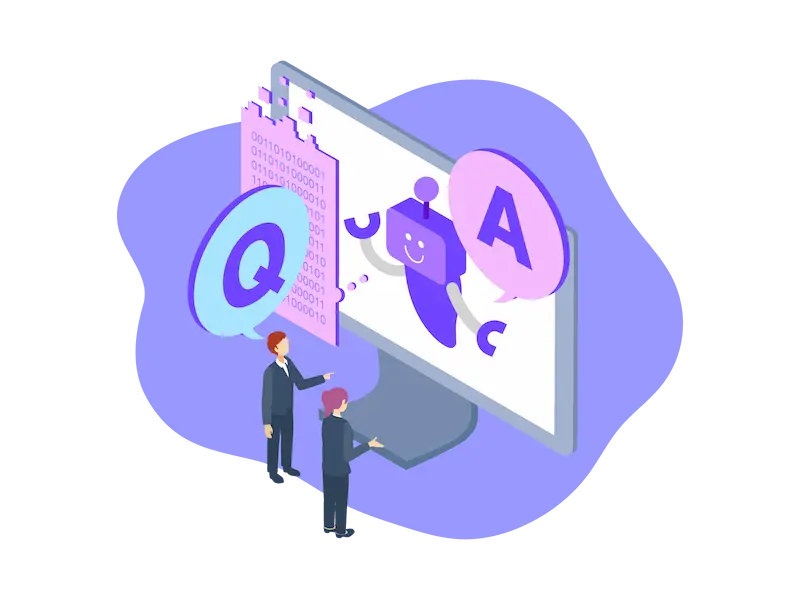
「AIの導入は難しそう」「予算や人員の問題で導入できるか不安」という声もよく聞かれます。しかし、実際の導入プロセスはそれほど複雑ではありません。段階的に進められる3つのステップをご紹介します。
Step 1. 現状の整理と資料の提供
まずは、既存の住民対応資料(FAQ集、窓口対応マニュアル、申請の手引きなど)を整理します。
すでに電子化されていれば、そのままAIに読み込ませることができます。紙の資料しかない場合も、スキャンしてPDF化するだけで対応可能です。
この段階で、「特に問い合わせの多い業務」「担当者不在時に困る業務」など、優先的に対応したい領域を明確にしておくと、より効果的な導入が可能になります。
Step 2. AIの学習と調整
提供された資料をもとに、AIが自動的に学習を行います。この段階では、技術的な専門知識は必要ありません。自治体の特性や住民からの質問パターンに合わせて、AIが適切に回答できるよう調整が行われます。
Step 3. 運用開始と改善
AIの導入後も、継続的な改善が重要です。住民からの新たな質問パターンや、未対応だった問い合わせなどを追加学習させることで、徐々に回答精度が向上していきます。
最初は庁内での試験運用から始め、徐々に住民向けサービスとして展開していくというステップを踏むことで、リスクを最小限に抑えながら導入効果を最大化できます。
まとめ:身近になったAI活用の第一歩
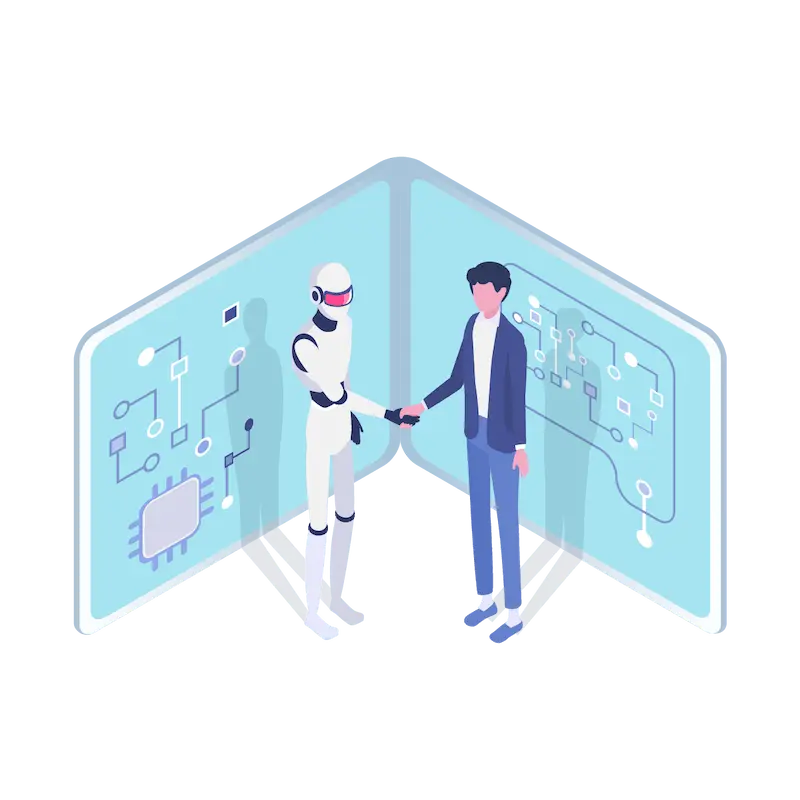
RAG型AIの導入は、もはや「先進的な取り組み」ではなく、多くの自治体で検討・導入が進む現実的な選択肢となっています。
限られた人員と予算の中で住民サービスの質を維持・向上させるためには、こうしたテクノロジーの活用が不可欠です。特に近年の人材不足や業務の複雑化を考えると、AI導入による業務効率化は避けて通れない課題と言えるでしょう。
重要なのは、AIを「人の代替」ではなく「人の補助」と位置づけ、職員の皆さんが本来の専門性を発揮できる環境づくりに活かすという視点です。
「住民満足」と「職員の働きやすさ」を両立させるRAG型AIの導入は、自治体DXの飛躍的な第一歩となるでしょう。
属人化を解消し、住民対応を革新: AIが実現する「誰でも正確な住民対応」を無料デモで体験する。詳細はこちら
これからの自治体業務を支えるシステム:RAGNIZE(ラグナイズ)
弊社が提供するRAGNIZEは、自治体業務の実情を理解した上で開発された、使いやすさを重視した区民相談AIソリューションです。
主な特徴
- 既存資料をそのまま活用:すでにお持ちのFAQ・手続き文書・内部資料をそのままアップロードするだけで、AIが自治体特有の情報を学習
- 多様な問い合わせ対応:窓口・電話・ウェブサイトなど、様々な問い合わせチャネルで一貫した対応が可能
- 簡単管理:専門知識がなくても、制度改定やお知らせを管理画面から簡単に更新でき、常に最新情報を提供
- 自治体向けセキュリティ対応:行政情報を扱うための厳格なセキュリティ基準に対応。オンプレミスや国内クラウドなど、自治体のポリシーに合わせた環境選択が可能
- 短期間での導入:最短1ヶ月で本番稼働が可能。IT部門がない自治体でも安心して導入いただけます
「電話対応に追われる毎日から解放されたい」「担当者不在時でも住民に正確な情報を提供したい」「制度改正のたびの情報更新が大変」といった自治体の皆さんの声に応える解決策を提供します。